|
書 籍
|
|
書籍名:-これからの国語科教育はどうあるべきか-
発 行:東洋館出版
発行年:2024(令和6)
ISBN-13: 978-4-49105-383-7
大学生協,または書店で購入してください。税込み2,090円
|

|
|
福田由紀 共著
その中の「心理学の世界から読書教育をとらえると―物語・小説を中心に―176-179頁」を執筆しました。
|
|
書籍名:-教育心理学-
基礎基本シリーズ
発 行:大学教育出版
編著者:原田 恵理子
福田 由紀
森山 賢一
発行年:令和4(2022)年10月
ISBN-13:978-4-86692-225-6
大学生協,または書店で購入してください。税込み2,200円
|
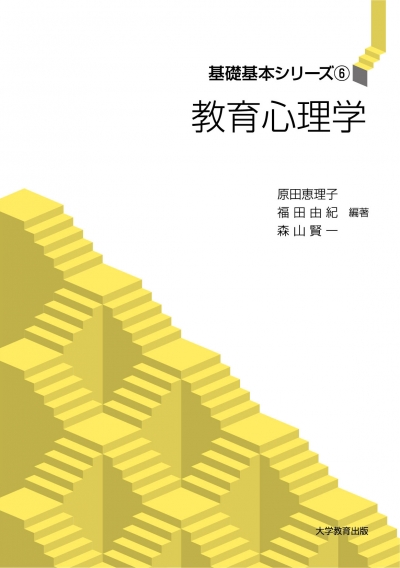
|
|
本書は,児童生徒と教員の両面から要点をつかむことができる構成となっています。
|
|
書籍名:-読書教育の未来-
発 行:ひつじ書房
著 者:日本読書学会編
発行年:2019(令和元)
ISBN-13: 978-4894769380
読書教育の未来
ここ,または書籍表紙画像をクリックすると本書購入サイトが開きます。税込み5,500円
|
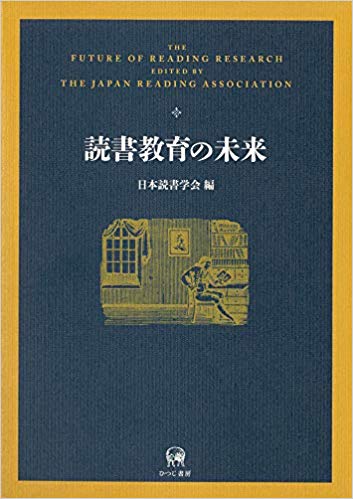 
|
|
本書は日本読書学会によって編集され,読書にまつわる事象について,言語心理学や脳科学から国語教育にわたる広範囲の内容を凝縮した本です。
その中の「第2章 6 読みと感情(Pp.144-154)」を執筆しました。また,第2章全体をまとめ役として携わりました。
「読みと感情」では,登場人物の感情理解と読み手の感情も関する研究を紹介しています。
|
|
書籍名:-言語心理学入門-
副 題:言語力を育てる
発 行:培風館
著 者:福田由紀 編著者
発行年:平成24(2012)年
ISBN-13:978-4-563-05231-7
書籍表紙画像をクリックすると本書購入サイトが開きます。または,大学生協,書店で購入してください。税込み2,970円
|

|
|
本書は,大きく3部構成になっています。
第1部 主に言語力をどのように育んでいるのか,実践的な研究を紹介しています。
まずは,気軽にお読みください。そうすると,言語力とは国語の科目だけで
必要とされているものではない!ことがわかるでしょう。
第2部 実践研究を支えているのは,言語心理学の基礎的な理論や知見です。言語力
の基礎となっている読み書き研究を紹介します。
専門用語が増えますが,ここを越えれば基礎知識を身につけられます。
第3部 2部までは,定常発達しているヒトの言語力に関して概観しました。その知
識を武器に,「支援」を考えてみましょう。
そして,序章には言語心理学の大御所であるキンチらが,自らの理論を米国で実践し
ている様子を寄稿してくれました。
日本語に訳されていますので,誰でも,基礎研究がどのように実践に活かされている
かがわかります。
「言語力」という日常生活に欠かせない能力を心理学する。それが本書です。
|
|
書籍名:心理学要論
副 題:こころの世界を探る
発 行:培風館
著 者:福田由紀 編著者
大学生協,または書店で購入してください。税込み2,310円
|

|
|
この本の特徴は
①索引が充実している
②歴史が熱い?!
③相互参照ができる
④通常の概論書よりも一歩踏み込んだ内容が記載されている
⑤扉べージを気軽に読んでも心理学が学べること。
①索引の数は非常に多く,同時に英語綴りも併記されているので,大学院受験や公務員の心理職受験に役立つ。
②心理学は突然生まれたわけでなく,それまでの経緯を知らないと深い理解ができない。そのため,ギリシア時代から遡っている。しかし,心理学の歴史はたかだか百数十年である。この際,心理学史に詳しくなろう。
③教科書は前から読むものではない!あっちのページを見たり,こっちのページに書いてあったかな?と本をめくることが大切。それを支援するのが文中の相互参照。
④執筆者の個性が光っているのもこの本の特徴。古典的なところを押さえつつも,執筆者の顔が見え隠れしている。第7章のように『ことばや思考』だけに1章費やしているもの特徴だし,今話題の認知行動療法についても入門とはいえ,詳細に書かれている。
⑤扉ページには,非言語的コミュニケーションのことがシリーズもののコラムとしてイラストとともに記載されている。これをぱらぱら見るだけでも,コミュニケーションの一端に触れられる。
|
|
書籍名:図で理解する発達
副 題:新しい発達心理学への招待
発 行:福村出版
図で理解する 発達-新しい発達心理学への招待-
ここをクリックすると本書購入サイトが開きます。税込み2,530円
|
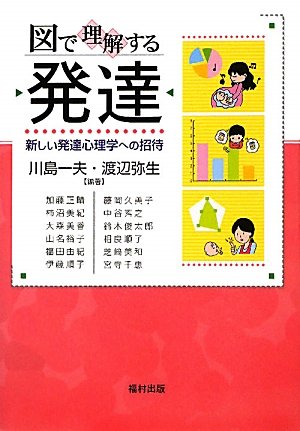
|
|
「この本では6章「ことばがいみをもつために -言語と思考の発達-」だけを執筆しました。分量は少ないですが,新たなデータを取り入れながら楽しく書いた原稿でした。新たなデータは,自分の小学校1年生や4年生のノートから選びました。これらのノートを眺めつつ,どのように書こうかな?と思っていた時が一番良かったです。書くとなると大変でしたが・・・。案外,昔の頃のノートは捨てて大人になると手元にないものですが,もし保存してある場合には,心理学的観点から是非見直してください。自分も人類の一部(みんな同じ発達過程を経ている)であると実感できるし,成長したなぁって感じますよ。」
|
|

Copyright(c) Hosei University Fukuda Psychology Research Lab. All rights reserved.
|

